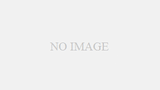今回は、3年の制作期間を経て、ダークソウルの制作にも関わっていたハイタカという人が、ほぼ1人で作った「地罰上らば竜の降る」という作品の体験版がネットをにぎわせているということで、まとめもかねて記事にしていく。
ちなみに、筆者はPCゲーマーでもなく、本作をプレイできる環境にないため、ネットの評判をまとめたりして、感想を述べる完全にエアプレイであるという前提で見ていただきたい。本来はしっかりプレイしてレビューするのが、筋であるというのは理解しています。
あと、こうやって記事にするのは心のどこかで、PS5でもリリースしてほしいなという考えがあるからです。講談社からのバックアップがあれば、実現性はありそうですが。
ブラッドボーン エンディング後の感想 2はありえるのか?ボスの順番やレベルデザインのすばらしさ
エルデンリング クリア後に振りかえる 強さランキング おもしろいボス つまらないボスはいるか?
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE セキロの難しさ、戦闘の肝とセキロは究極のオンラインゲームだったという話
地罰上らば竜の降る youtuberの評価などの総括
ゲームメディアも含め、多くの目の肥えたり、業界人のyoutuberも地罰上らば竜の降るの体験版を心待ちにし、プレイした感想などを動画にあげている。
ハイタカ氏も、製品版につなげるために忌憚のない意見を体験版で募られていた。
今回の体験版は、アクションRPGをゴールにつくられているが、特に戦闘面に特化した体験版です。
ネットの評判や評価を雑にまとめると
- 1人で3年間製作している努力と根気は応援したい
- 格闘ゲームのように複雑な操作性で、将来的に対人戦を意識していると思うが、成立するのか?
- パリィの方向が4方向と、他のゲームに比べて複雑にもかかわらず、敵攻撃の予備動作がわからず難しい
- ジャスト回避が難しず、敵の攻撃がやむのを待つ傾向にある
- 攻撃の種類が非常に豊富なのだが、最終的に隙の少ない技で連打すればいいとなってしまう
- 本作独自の魔法を使い続けると地罰というオブジェがあらわれ、大ダメージのペナルティがあるのだが、自分が出した地罰や相手が出した地罰双方に当たり判定がある。これは仕様なのか?
- チュートリアルが親切とは言い難く、相手はすべてわかった状態で攻撃してくるので、とにかく難しい
特に素晴らしいレビューをされているなと感じたのは、ゲームプランナーをされている方のレビューになります。
いろいろな動画を拝見しましたが、手放しで評価、大絶賛というものはあまりなく、逆に手厳しい意見が多かったように見えます。
しかし、これは体験版であり、ここからシステムを洗練したり、ブラッシュアップするため、これが炎上だったりするわけではなく、さらによくなる作品になってほしいというyoutuber側の願いでもあります。
全員が共通する認識として、ハイタカさんにぜひともこの作品を完成させてほしいという想いが強いのです。
地罰上らば竜の降る IGNJAPANより 完成への可能性について
ゲームレビューサイトを運営しているIGNでは、youtubeのタイトルで、はっきりと残念な出来と記載されています。
こちらもただ非難しているわけではなく、体験版はどのような反省をすべきなのかを示唆するメッセージが込められています。
IGNの今井氏は、どのように遊ばせたいのかというコンセプトが不明瞭で、メカニクスだけがゲームの面白さだと思うのは、間違いで、メカニクスも絞り切れないという点を指摘されています。
あとは取捨選択、クラウドファンディングや講談社からの支援があったとして、その製作費で作品を作りきることができるのか?
対人戦とソロプレイを両立させることは、フロムでさえも難儀していたので、どちらかに絞ることはできないのか?
アクションRPGを目指されているが、割り切ってアクション一本として制作することはできないか?
などなどが議論されました。
世界一おもしろいアクションゲームとは何か?
ハイタカ氏が目指している世界一おもしろいアクションゲーム
元フロム社員ということもあって、死にゲーから着想を得ている部分が多いですが、私個人がおもう面白いアクションゲームについてちょっと振り返ってみます。
ストリートファイター3
ストリートファイター3は、初心者同士だと、キャラクター選択時にどのスーパーアーツ(スーパーコンボ)を選択するのか?
どこのタイミングでEX必殺技を使うのか?
そして相手の簡単な癖を呼んで、ブロッキングを仕込むという楽しみもできます。
体力が現代の格闘ゲームに比べて低いため、ブロッキングの濃密な攻防を楽しみ切らずとも戦えるのが素晴らしい点です。
一方で、上級者同士になるとさらに深い攻撃の読みあい、ブラフなどの詰将棋のような心理戦も展開されていきます。
このように、初心者~上級者まで遊びの幅がありながらも、操作はシンプルというのが1つの完成形かと思われます。
SEKIRO
今まで、敵の攻撃にタイミングをあわせてカウンターするパリィというシステムが、ソウルボーンでは主流でした。
SEKIROでは「弾き」という守備的なシステムになっています。弾きを決め続けることで、相手の体幹ゲージを減らして、最後まで減らしきると一撃で倒すことが可能です。
弾きと体幹はSEKIROの根幹といえるシステムで、本当はこのシステムを十二分に使って倒してほしいのでしょう。
しかし、効率を狙うのであれば、弾きからの必殺で倒すのがいいのですが、モンスターハンターのように敵の周りをぐるぐる回って、ヒットアンドウェイや、忍具でのごり押しなども許されているゲームバランスになっているのが、SEKIROの魅力です。
もちろん、過去のソウルボーンからエルデンリングも、積極的にパリィするか、逃げ回って隙を見出すかという戦い方の振れ幅はあるものの、SEKIROはその幅をさらに広げて、すみわけを作れた作品だと思います。
両者に共通する点として、初心者は初心者の楽しみができて面白く感じ、上級者も同様の感じ方ができるという点です。
これは完全に分かれているわけではなく、ある日初心者が、ブロッキングや弾きに目覚めて、ゲームにのめり込めることも許容しています。
地罰上らば竜の降る ハイタカ氏の魅力とインディーゲームの課題について
地罰は、いわばインディーゲームであり、近年のインディーゲームは、グラフィック、操作性、ストーリーにとにかくこだわった作品が増えていますが、製作期間もかなり少数で行う分、非常にかかっているように見受けられます。
ビジネスとして考えると、定められた製作費と期間の中で、形となるものを作り出さなければなりませんし、ハイタカ氏にとって講談社のネームバリュー、バックアップなどはもちろんプラスには働いていますが、限られた時間のなかで作る難しさも感じられます。
ある意味、ゲーム制作というリアリティショーをリアルタイムで見ているという没入感が、ハイタカ氏の動画の面白さの肝になっているのですが、今後の動向に注目ですね。
ブラッドボーン エンディング後の感想 2はありえるのか?ボスの順番やレベルデザインのすばらしさ
エルデンリング クリア後に振りかえる 強さランキング おもしろいボス つまらないボスはいるか?
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE セキロの難しさ、戦闘の肝とセキロは究極のオンラインゲームだったという話